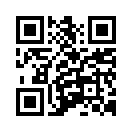2018年05月09日
春の青森にお邪魔して…
この度は下山社長ご夫妻には大変お世話になりありがとうございました。
また北川さんには、青森の魅力や静岡では見られない風景などをたくさん紹介して頂き感動の連続でした。それぞれの気候風土に培われた自然遺産を大切にその魅力を伝えて行く観光タクシーの役割の大きさを学ばせて頂きました。
車窓からですが…
リンゴ畑と岩木山の風景がご当地らしくて。見る方角によって山の形が全然違います



岩木山神社
津軽富士とも呼ばれる美しい岩木山のふもとにある神社で、創建約1,200余年の歴史を持っています。
岩木山神社は、本州最北端の鎮守様の木材・県産のヒバを使用し、古いものは390年の風雪を耐えた建造物です。
岩木山を望む鳥居から本殿までの長い参道は、杉木立に囲まれています。青森観光情報アプティネットより
何回かの焼失を経て、藩政時代に再建された社殿は重厚で「奥の日光」という異名を取るほど秀麗です。旧暦8月1日を中心に行われるお山参詣、津軽の象徴である岩木山は「お山」とか「お岩木様」と呼ばれ、津軽の人々の信仰の山です。


鶴の舞橋の上から岩木山を望む

鶴の舞橋
鶴の舞橋は平成6年7月8日、岩木山の雄大な山影を湖面に美しく映す津軽富士見湖に、日本一長い三連太鼓橋「鶴の舞橋」として架けられました。全長300メートルもの三連太鼓橋はぬくもりを感じさせるような優しいアーチをしており、鶴と国際交流の里・鶴田町のシンボルとして、多くの人々に愛されています。
岩木山を背景にした舞橋の姿が鶴が空に舞う姿に見えるとも言われ、また、橋を渡ると長生きができるとも言われています。夜明けとともに浮かび上がる湖面の橋の姿や、夕陽に色づく湖と鶴の舞橋は絶景で、季節の移り変わりと共に多くの観光客たちの目を楽しませています。

岩木山の上の方にはまだ残雪が…


北川さんが車を走らせながら見つけてくれたピンクが美しいカタクリの花

蕗のとうも

海岸通りにはイカの干物作りが行われていました
イカは名物だそうですが、近年水揚げ量が減っているそうです

十二湖の青池
青森県側の白神山地西部に位置するブナ林に囲まれた33の湖沼群です。江戸時代に発生した大地震による山崩れによってできたといわれています。その際、大小33の湖沼ができましたが、崩山から眺めると12の湖沼が見えたことから十二湖と呼ばれるようになりました。青いインクを流したような色といわれる青池が特に有名です
この日は曇り空だったので残念ながらインク色とまではいきませんでしたが

お日様が出ているとこんなにきれいに(北川さん撮影)
なぜこんな色になるかは、まだ解明されていないそうですが神秘的ですね

ブナ自然林 芽吹きの時のブナ林は緑が柔らかく清々しいです
ここでポスターの撮影をされたと聞きました

自然林の両脇には可愛い山野草が見られます





千畳敷海岸
広く平らな場所であることから、畳千畳分という意味で名づけられた「千畳敷」。有名なアルプスの「千畳敷カール」を始めとして、この名が冠せられた地名は全国各地にあるが、青森県西津軽郡にある「千畳敷海岸」は夕日の名所としても名高い景勝地。かつての藩主が、この千畳敷を利用して大宴会を開いたとの逸話も残る場所だ。1792年に起きた大地震により、海底が最大で3.5メートルも隆起して出来上がったといわれる。恵比寿岩、かぶと岩などと名づけられた独特の形をした奇岩の連なる海岸線が12キロに渡って続く様は圧巻だ。潮の干満により出来上がった潮溜まりが各所に見られ、また複雑に入り組んだ岩場に打ち寄せた波が大きく吹き上がる「潮吹き」も見られる。

恵比寿岩

潮吹き岩

観光列車は千畳敷海岸で観光客を降ろししばらく止まっていました

20分ぐらい停車していたでしょうか、観光客を乗せ再び出発!

忘れられないのが、樹齢1,000年以上の大イチョウ
この大きさには感動します!桜の樹齢も100年以上の古木が多いのに驚きましたが青森の木々は寿命が長いですね。環境でしょうか?



垂乳根(たらちね)と言われる由縁は、見てのとおりです

竜飛岬 ここも忘れられない場所
北川さんに風が強いと聞いていましたが、今まで台風でも経験したことの無い強風にビックリ!

丁度この下を青函トンネルが走っているそうです

この辺りは潮の流れが速く左から右へと川のように流れています

歌が流れますが、恐ろしいほどの強風で少し離れると何も聞こえません。カメラを持つ手も風で揺れてしまいます

この方は、太宰治の孫だと伺いました。3年前に斜陽館へ行きました

青函トンネルの入り口です


帰りに… こちらは岩手山

また北川さんには、青森の魅力や静岡では見られない風景などをたくさん紹介して頂き感動の連続でした。それぞれの気候風土に培われた自然遺産を大切にその魅力を伝えて行く観光タクシーの役割の大きさを学ばせて頂きました。
車窓からですが…
リンゴ畑と岩木山の風景がご当地らしくて。見る方角によって山の形が全然違います
岩木山神社
津軽富士とも呼ばれる美しい岩木山のふもとにある神社で、創建約1,200余年の歴史を持っています。
岩木山神社は、本州最北端の鎮守様の木材・県産のヒバを使用し、古いものは390年の風雪を耐えた建造物です。
岩木山を望む鳥居から本殿までの長い参道は、杉木立に囲まれています。青森観光情報アプティネットより
何回かの焼失を経て、藩政時代に再建された社殿は重厚で「奥の日光」という異名を取るほど秀麗です。旧暦8月1日を中心に行われるお山参詣、津軽の象徴である岩木山は「お山」とか「お岩木様」と呼ばれ、津軽の人々の信仰の山です。
鶴の舞橋の上から岩木山を望む
鶴の舞橋
鶴の舞橋は平成6年7月8日、岩木山の雄大な山影を湖面に美しく映す津軽富士見湖に、日本一長い三連太鼓橋「鶴の舞橋」として架けられました。全長300メートルもの三連太鼓橋はぬくもりを感じさせるような優しいアーチをしており、鶴と国際交流の里・鶴田町のシンボルとして、多くの人々に愛されています。
岩木山を背景にした舞橋の姿が鶴が空に舞う姿に見えるとも言われ、また、橋を渡ると長生きができるとも言われています。夜明けとともに浮かび上がる湖面の橋の姿や、夕陽に色づく湖と鶴の舞橋は絶景で、季節の移り変わりと共に多くの観光客たちの目を楽しませています。
岩木山の上の方にはまだ残雪が…
北川さんが車を走らせながら見つけてくれたピンクが美しいカタクリの花
蕗のとうも
海岸通りにはイカの干物作りが行われていました
イカは名物だそうですが、近年水揚げ量が減っているそうです
十二湖の青池
青森県側の白神山地西部に位置するブナ林に囲まれた33の湖沼群です。江戸時代に発生した大地震による山崩れによってできたといわれています。その際、大小33の湖沼ができましたが、崩山から眺めると12の湖沼が見えたことから十二湖と呼ばれるようになりました。青いインクを流したような色といわれる青池が特に有名です
この日は曇り空だったので残念ながらインク色とまではいきませんでしたが
お日様が出ているとこんなにきれいに(北川さん撮影)
なぜこんな色になるかは、まだ解明されていないそうですが神秘的ですね

ブナ自然林 芽吹きの時のブナ林は緑が柔らかく清々しいです
ここでポスターの撮影をされたと聞きました
自然林の両脇には可愛い山野草が見られます
千畳敷海岸
広く平らな場所であることから、畳千畳分という意味で名づけられた「千畳敷」。有名なアルプスの「千畳敷カール」を始めとして、この名が冠せられた地名は全国各地にあるが、青森県西津軽郡にある「千畳敷海岸」は夕日の名所としても名高い景勝地。かつての藩主が、この千畳敷を利用して大宴会を開いたとの逸話も残る場所だ。1792年に起きた大地震により、海底が最大で3.5メートルも隆起して出来上がったといわれる。恵比寿岩、かぶと岩などと名づけられた独特の形をした奇岩の連なる海岸線が12キロに渡って続く様は圧巻だ。潮の干満により出来上がった潮溜まりが各所に見られ、また複雑に入り組んだ岩場に打ち寄せた波が大きく吹き上がる「潮吹き」も見られる。
恵比寿岩
潮吹き岩
観光列車は千畳敷海岸で観光客を降ろししばらく止まっていました
20分ぐらい停車していたでしょうか、観光客を乗せ再び出発!
忘れられないのが、樹齢1,000年以上の大イチョウ
この大きさには感動します!桜の樹齢も100年以上の古木が多いのに驚きましたが青森の木々は寿命が長いですね。環境でしょうか?
垂乳根(たらちね)と言われる由縁は、見てのとおりです
竜飛岬 ここも忘れられない場所
北川さんに風が強いと聞いていましたが、今まで台風でも経験したことの無い強風にビックリ!
丁度この下を青函トンネルが走っているそうです
この辺りは潮の流れが速く左から右へと川のように流れています
歌が流れますが、恐ろしいほどの強風で少し離れると何も聞こえません。カメラを持つ手も風で揺れてしまいます
この方は、太宰治の孫だと伺いました。3年前に斜陽館へ行きました
青函トンネルの入り口です
帰りに… こちらは岩手山